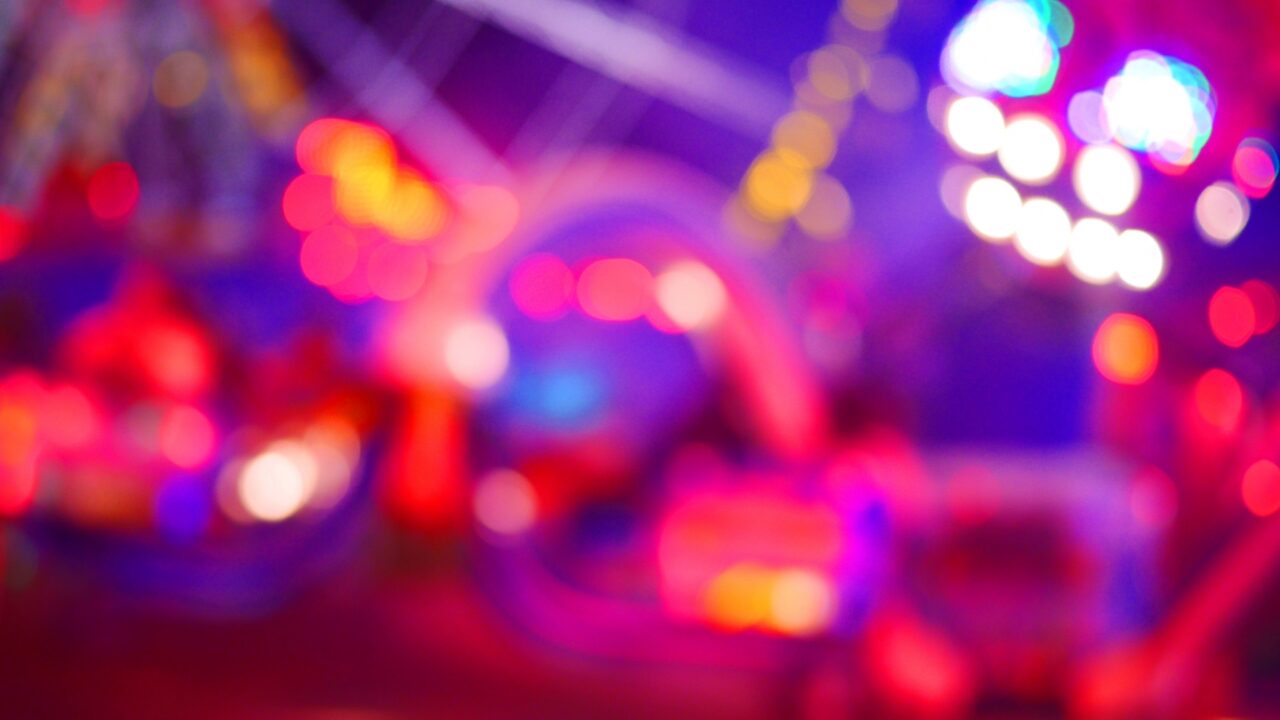家庭の中が戦場だった子供の頃の私の安心できる場は外にあった。図書室だったり、保健室だったり、放課後の教室だったり。
そんなわたしの家の外にある、安心できた居場所の中のひとつが、本八幡駅南口にあったゲームセンターだった。
私の父はJR本八幡駅の近くで英会話の教室を経営していた。実家からバスで15分くらいの場所にあるその教室に、私は小学生の頃から通っていた。
中学生になってからスタートの時間は少し遅めになった。7時とか。英会話の授業のある日は学校から帰ってきてしばらく家で過ごし、時間になると1人でバスに乗って駅に向かう。
授業自体が終わるのは8時過ぎくらい。そのあと、ゲームセンターに寄ってしばらく遊んでから帰路に就くのがお決まりのコースだった。
そもそも私がゲームセンターを好きになった理由は、小さい頃からニッケコルトンプラザというショッピングモールの中のゲームセンター(らんらんらんど)で遊んでいたからだと思う。
母は買い物に行き、私と弟だけで存分にうろうろできる。お金の分だけ好きにしていい。その自由さと、家にはない底抜けの謎のハッピー具合が妙に私の心を癒してくれたものだった。
しかし、本八幡の南口にあったそのゲームセンターは、らんらんらんどとは真逆の、薄暗く、タバコを吸う大人がいっぱいいる、ハードボイルド目な、いわゆる「ゲーセン」だった。
いつでも空気が重く停滞しているお世辞にもキレイとは言えないゲーセンの暗闇の中で、誰もが1人客で、ゲームの台にじっと向き合っていた。
表の路地に面した場所と自動ドアのすぐ近くには客寄せ用と思われるUFOキャッチャーが何台か並んでいる。一歩奥に足を踏み入れるとスロットやパチンコといったメダルのゲーム台が奥の壁沿いに並んでいる。その横には対戦ゲームの筐体もあった。
真ん中には大きなビンゴゲーム。私はこのビンゴゲームがとても好きだった。(BINGO PLANETの動画)
ゲーセンのビンゴゲームといっても、ビンゴの抽選方法はいたってアナログだ。
広い穴の開いた回転盤が真ん中にあり、ゲームがはじまると、端っこからアクリル製のボールが、まずは3つ排出される。
ボールは、しばらく回転盤のふちを回りながら、少しずつ中心に落ちてくる。途中にある番号が書いてある穴にボールが落ちれば、その番号が確定となる。
固いボールはすぐには番号が書かれた穴に落ちず、中心の回収穴に落ちて何度も再抽選なったりする。
5つのボールが全部穴に入るまでには結構時間がかかる。今っぽい言い方をすれば「時間が溶ける」ゲーム。
私は、このビンゴゲームがとても好きだった。いつまでもやっていたかった。家に帰りたくない気持ちもあったけれど、それより無心で目の前の出来事に没頭していいのが有り難かった。もちろんお金は使うけれど、時間がかかる分ゆっくり無くなるし、たまにビンゴで当たればまた長くできる。
時間をかけて、何度も繰り返し、照明に照らされたビンゴのボールがきらきらと光りながら回転盤の上をすべる。気持ちをあおるような演出の音楽の間に、アクリルのボールがぶつかり、穴からこぼれ、カタカタと音を立てる。
回転盤を囲むようにシートがあり、全員、当たろうが外れようが、静かに1回1回のゲームを消費していた。
今思えば、中学生の女の子が繁華街にある夜のゲーセンで1時間も2時間もゲームをしていて、周りの大人が気にならないわけがないと思う。でも、誰にも一度も話しかけられたことはないし、嫌な思いをすることもなかった。
私は「大人が居て、なおかつ私に対して無関心でいてくれる場所」を欲していたと思うのだ。
母は常に私の挙動にひどく関心があり、私が、母自身を否定するような動きを少しでも見せようものなら、怒るか、叩くか、まれに泣くか、だった。
何が母の琴線に触れるか分からないで生きるのはどこに地雷が埋まっているか分からないで進む戦場と同じだ。一秒たりとも安心できない。
図書室では司書さんが。保健室では保健室の先生が。放課後の教室ではテストの丸付けをしている先生が、それぞれ私の存在を感じながらも無関心でいてくれた。小学生の私の大事な居場所だった。
本八幡のゲーセンも同じように、中学生の私に居場所を与えてくれた。大人の無関心という繭が私を抱きとめてくれていた。もちろん本当に無関心かどうかは別だけど、これは大人になった今だからわかること。当時の私は、放っておかれたかった。そうじゃないと息ができなかったから。
あの時はなぜこんなにも「1人で外で居る」ことに安らぎを覚えるのか分かっていなかった。図書館に行くことも、買い物に出かけることも、本屋さんに居ることも、全部が私の自由の象徴だったんだ。
だけども、明るく全てを見透かされるような陽の光の下では、私の抱えている仄暗さが目立ってしまうことも知っていた。心の闇を、子供の頃の私は無意識に恥と感じていて、だからこそ同じような暗さのある、何も言わずとも受け入れてくれるゲーセンが一番のシェルターになったのだ。
母は「監視」「コントロール」「執着」を愛と言った。今の私は、絶対にそれを認めない。私は死ぬまで自由を求める。愛は自由のことだから。自由が伴わないものはそもそも愛ではないのだから。
「正しい無関心」は愛だと、あのゲーセンが居場所になって生き延びることができた私は強く思う。
表面だけ見ていては分からないことがある。それを理解できたという意味でも、私は、死なずに大人になって良かったなと思う。
今ではそのゲーセンは別のお店になり、本八幡駅南口の陰鬱さは払拭されつつある。路上駐輪が多すぎて歩くのが大変だった雑多な駅前の、ネオンやら酔っ払いやお姉さんらの喧騒の中にロウソクの炎のように静かに存在してくれていた私の居場所はない。
けれど、私の心の中には永遠に存在している。
消えずに。
時々、私はそこに帰るのだ。私の大切な自由を思い出すために。